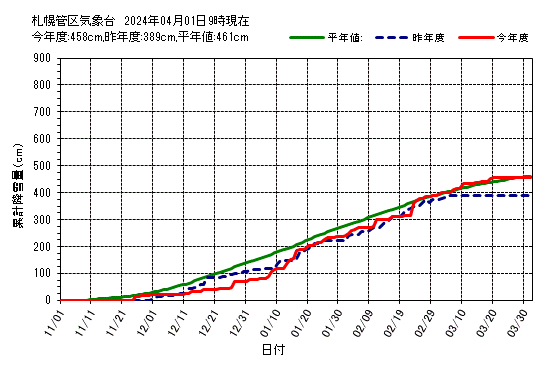5月25日は仕事が休みの日なので野菜苗を畑(庭)に植えようと思っていました。 ところが本州は真夏並みの暑さになるというのに、こちら札幌は気温がかなり低くなる予想だったので、野菜苗の植え付けを止めました。 実際、25日の最高気温は15.3℃とこの時期としてはかなり低く、野菜苗を植える天候(気温)ではありませんでした。
以下の表は2015~2023年までの9年間の我家の家庭菜園で野菜ポット苗を植えた月日とそのときどきの気温です。
| 年度 | 月日 | 平均気温 | 最高気温 | 最低気温 |
| 平成27年(2015) | 5月23日 | 17.8 | 21.7 | 13.6 |
| 平成28年(2016) | 5月19日 | 17.6 | 24.1 | 12.2 |
| 平成29年(2017) | 5月20日 | 17.2 | 25.4 | 13.7 |
| 平成30年(2018) | 5月22日 | 18.9 | 26.9 | 12.2 |
| 令和元年(2019) | 5月23日 | 18.1 | 24.5 | 12.0 |
| 令和2年(2020) | 5月29日 | 17.8 | 23.6 | 11.8 |
| 令和3年(2021) | 5月26日 | 16.1 | 22.0 | 9.9 |
| 令和4年(2022) | 5月26日 | 20.6 | 27.9 | 15.2 |
| 令和5年(2023) | 5月25日 | 18.1 | 26.2 | 8.5 |
| 令和6年(2024) | 5月25日 | 11.0 | 15.3 | 8,0 |
この表を見ると、我家の野菜苗の定植時期は、おおよそ、平均気温が17℃以上、最低気温が10℃以上の、時期は5月20日以降となっており、今年5月25日の気温は野菜苗を定植するには気温が低かったようです。
ホーマックなど園芸店では、5月上旬(ゴールデンウィーク)から野菜苗を販売しています。 企業として早く売りたい気持ちは分かりますが、商売とは言えあれは早すぎます。
最近は、野菜苗を植える前にビニールマルチを張って、かつ、定植後円筒状ビニール風除けを設置して、野菜苗を寒さから保護することが多くなっています。 しかし、そのような資材の無かった頃(使わなかった頃)は、キュウリの定植時期は6月中旬の札幌祭り(北海道神宮祭)頃と言われていました。
キュウリの苗を早い時期に植えると、苗が萎れて最後に枯れてしまうことがあります。 この原因は、キュウリは葉の面積が大きいのでそこからの蒸散量も多くなるのですが、5月上中旬の気温の低い時期に植えると、当然地温も低いためにキュウリの根は土壌中の水分を吸い上げる力が低くなっているのです。 ところが、葉は蒸散を続けているので、キュウリ体内での水分バランスが崩れて葉が萎れるのです。
トマトは葉の形状を見てわかる通り、キュウリの葉に比べ葉の面積が小さく、また乾燥にも強いため、札幌の5月に周期的にやってくる来る寒さにも比較的耐性があり、5月20日前後に植えてもほとんど問題はないのです。 しかし、キュウリの定植はどうあろうと6月上旬以降にすべきです。 この時期に定植するにしても、やはり、植える場所をビニールマルチで被うって地温を上げてからの方がより安全と思われます。
<トマト苗について>
 2024.5.26
2024.5.26
写真のトマト苗は、我家で育てたものです。
①4月4日 :は種(セルトレイ)
②4月27日:1回目移植(セルトレイ → 6㎝ポリポット)
③5月7日 :2回目移植(6㎝ポリポット → 9cmポリポット)
苗の大きさは、草丈が約30cmで、本葉が8枚出ています。 頂点の小さな葉をかき分けると小さなつぼみが見えます。
トマトの苗を購入するときは、
①葉は7枚以上
②茎はしっかりと太く、節間が均等で、
③花が咲き始めている
このような苗を選びなさいと言われています。 我家で育てた苗は①の条件は満たしているものの、②の茎は細目で、節間は均等ではなく間延びしているし、③については小さなつぼみが見える程度で開花までにはまだしばらく時間がかかりそうです。専門の育苗ハウスで育てられた苗に比べると、一般住宅ではこんなものだと諦める?妥協しています。
しかし、ホーマックなどの園芸店で販売されている苗も、昔は花が咲いているポット苗があったのですが、最近はほとんど見かけなくなりました。さらに、苗自体も以前に比べると小振りになってきているようです。
 2024.4.7
2024.4.7 2024.4.7
2024.4.7 2024.4.7
2024.4.7 2024.4.7
2024.4.7 2024.4.7
2024.4.7
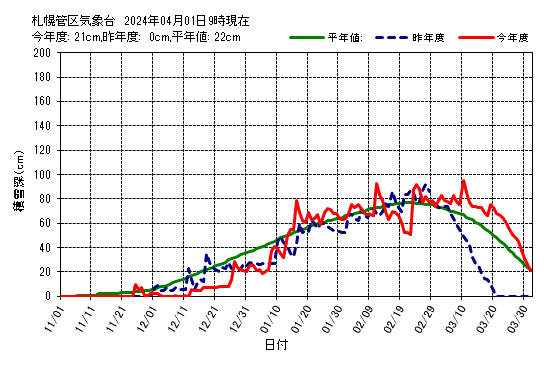
 2024.2.21
2024.2.21