約7年前に花が咲いていない透明のビニールポットに入ったコチョウランの株を買ったことがあります。 このコチョウランは、大輪系の白い花が咲くタイプです。
早速、ミズゴケで素焼鉢に植替えて、リビングの窓際で育てました。新葉も出てきて株は順調に育つのですが、1年経っても、2年経っても一向に花茎が出て来ない、花が咲かないのです。
ちょうどその頃に、何かのお祝いにコチョウランをいただきました。それは6月初め?頃のことです。小輪系タイプで薄ピンクの花が咲いていました。白の大輪系のコチョウランと同じ窓際に置いて育てました。白の大輪系コチョウランは相変わらす花が咲く気配を全く見せないのに、薄ピンクのミニタイプのコチョウランは6月に花が咲いてから半年後の、12月に再び花茎が伸びて1月から咲き始めました。 1年も経たない内に2度花を咲かせたのです。このコチョウランは、毎年、夏と冬に2度花を咲かせるのです。

2024.1.25 ミニコチョウラン
同じコチョウランでも、それぞれの株によってその開花習性は違ってくるようです。このような開花習性の違いはどのような理由によるものなのでしょうか?
その前に、コチョウランの自生地はどこで、どのような環境で生育しているのか調べて見ました。
🔵コチョウランの生育環境
〇 コチョウランの自生地
フィリピンやインドネシアなど東南アジアを中心とした高温多湿の熱帯地域
〇 コチョウランはどのような場所で育っているのか?
・コチョウランは樹木に着生するラン(着生ラン)で、地面ではなく、樹の幹や枝に根を張って、又はぶら下げて生育
・熱帯雨林の樹上で、強い直射日光を避けながら、言い換えると、ジャングルの木漏れ日の柔らかい光が注ぐ、森の中でも風が通る場所に生育
・熱帯雨林なので、年中暖かくて、昼と夜の温度の差がない環境
この温度環境は札幌のリビングルームと似ています。 気温は年間を通して20~28℃(最近は30℃を超える日も多くなったが)で、コチョウランにとって札幌のリビングは温度的にまあまあの環境といっていいのではないでしょうか?
それなのに白の大輪系は花を咲かせてくれません。
🔵 白の大輪系のコチョウランが花を咲かせない理由(ミニ系と大輪系の温度感受性の違い)
・ミニコチョウランは、低地の熱帯雨林に自生する原種が多く、夜間もあまり温度が下がらない環境に適応している。なので、温度変化にあまり敏感じゃなくて、比較的温度差が大きくない安定した環境でも花芽をつけやすい。
・一方、大輪系のコチョウランは、標高の高い場所に自生する原種(Phalaenopsis amabilis;ファレノプシス アマビィリス)の血を引いていて、昼夜の温度差がある環境で花芽を形成する性質が強い。 特に夜間に18℃前後まで下がるような環境が、花芽形成のきっかけになる
・札幌のリビングのように年間を通して温度が安定している環境では、大輪系は「季節が来た」とは気づかず、花芽をつけるタイミングを見つけられない可能性が高い
🔵 大輪系のコチョウランに花を咲かせるには?
秋〜初冬にかけて、夜間だけ少し涼しい場所(18℃前後)に2〜3週間置くと、花芽ができやすくなる。 具体的には、夜だけ玄関や廊下に移動させるとか、窓際で冷気が届く場所に置くなど、ちょっとした工夫・配慮が必要。
一つ付け加えると、大輪系のコチョウランは、花が大きいので株が充実していないと花芽をつけづらいので、夏場にしっかり育てることも重要
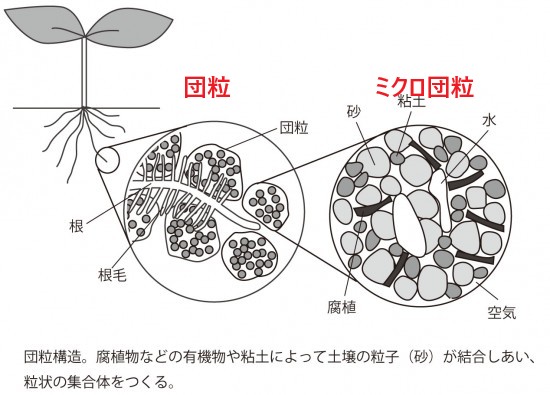
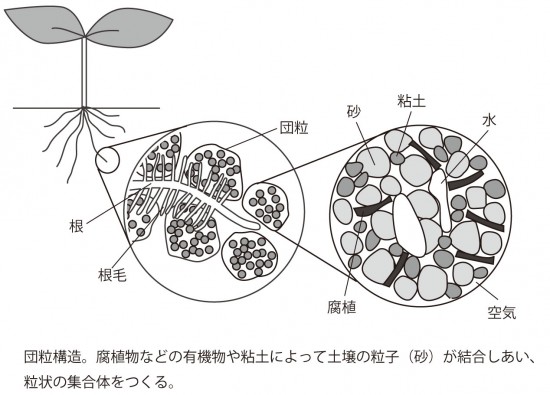
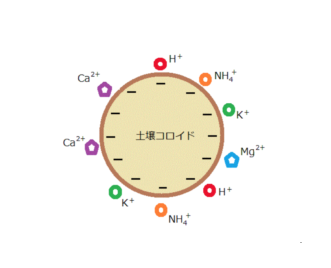
 2023.1.28
2023.1.28 2024.2.1
2024.2.1 2024.2.1
2024.2.1 2026.2.4
2026.2.4