 2013.2.10
2013.2.10
冬芽は、平滑でつやがある。 頂芽は大きく、卵形ないし五角錐形で、長さ3~8mmあり、開出し、上位ほど大きい。 頂芽の周囲には輪生状に数個の頂生側芽がつく。 芽鱗は托葉起源で、栗色ないし赤褐色をし、縁には短毛がはえ、25~35枚あり、5列に並び、覆瓦状に重なる。(落葉広葉樹図譜)
写真の冬芽は丸く見えますが、実際に手にとって見ると、もっと角ばっています。
 2011.2.4
2011.2.4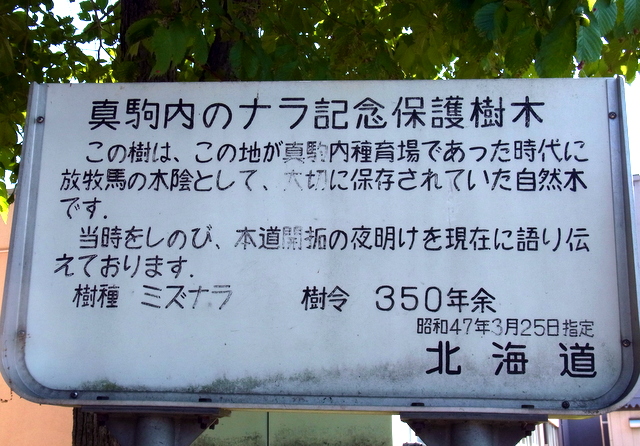 2011.7.1
2011.7.1 2011.2.27
2011.2.27.jpg) 2011.4.24
2011.4.24.jpg) 2013.2.10
2013.2.10 2011.5.8
2011.5.8 2011.5.21
2011.5.21 2011.5.30
2011.5.30 2011.6.3
2011.6.3 2011.7.1
2011.7.1 2012.7.14
2012.7.14 2012.7.14
2012.7.14